R3 騒音・振動特論 問18

問題
弾性支持による振動対策に関する記述として,不適当なものはどれか。
⑴ 起動から定常回転数に達するまでの時間が長いと共振点通過時に変位振幅が大きくなるため,共振時の振幅ができるだけ小さくなるように,減衰が大きい減衰材料を選定する。
⑵ ばね上が剛体であるとしたときの弾性支持系は,並進 3 自由度,回転 3 自由度の 6 自由度系となるが,設計を容易にするためには,連成を避けた弾性支持設計をする必要がある。
⑶ 機械の剛性が小さい場合は,機械を剛性の大きい架台で補強する。
⑷ 防振効果を確保するために,振動数比を√ 2 以上,一般的には 3 以上に設定する。
⑸ 衝撃加振力が働く場合には,機械本体に質量を付加して弾性支持することで, 固有振動数を低くして,地盤に伝達する力を小さくすることができる。
解説
知識を問う問題としては、難しい部類になると思います。
(1)
共振とは、固有振動数と機械の回転数が一致する状態です。
下の図において、振動数比が1の場合を指します。

問題文のとおり、共振時(振動数比=1)の振幅をできるだけ小さくするためには、減衰の大きい材料が適しています。
しかし、さらに回転数を上げていく(振動数比が大きくなる)と、減衰比の小さい方が振動伝達率も小さくなってしまいます。
⑷の記載されたとおり、防振効果を確保するために,振動数比は√ 2 以上,一般的には 3 以上に設定されます。
この防振域においては、減衰が大きいほど振動伝達率が大きくなり、防振効果が悪化します。
防振設計の目的は「定常運転時の振動を小さくすること」であり、起動・停止時の共振通過は一時的なものです。
このため、減衰を過度に大きくすると、防振本来の効果が損なわれることになります。
したがって、減衰の程度、固有周波数、起動スケジュール、支持剛性、質量配分、バランス、吸振器の導入などを総合設計することが必要になります。
(4)
防振域の振動数比についてはよく問われるので、覚えておきましょう。
(5)
固有振動数ですが、鉄琴や木琴をイメージして下さい。音が鳴るように叩く状態が共振です。低い音の板は大きいので、固有振動数が低い場合は重量も大きくなります。
解答.
1
次の問題だよ~♪

前の問題だよ~♪

目次に戻るよ~♪

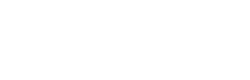


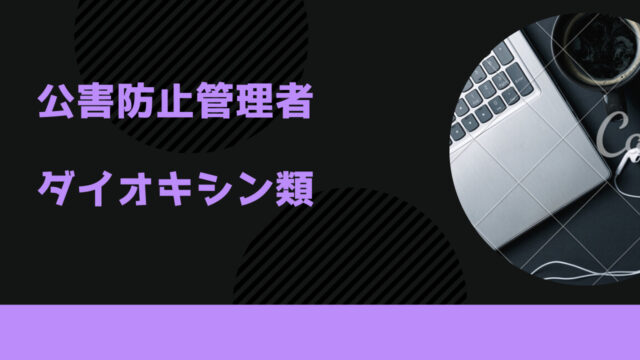
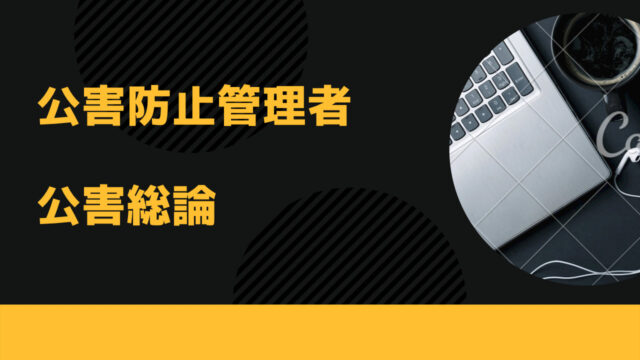

突然のコメント失礼いたします。1番の文章の中身自体におかしな点はないが、そもそも共振状態の振幅のみに着眼し対策を講じているという点が振動対策として不適切というようなことでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
実際の防振域は、共振の振動数より大きくなり(振動数比が√2以上)、共振状態は一時的に過ぎません。
ご質問のとおり、共振時のみ対策すると、実際の防振域では十分な効果を発揮できなくなるため、不適となります。
このあたりを含めて本文を追記したので、ご確認お願いします。