これで安心!公害防止管理者試験で役立つ常用対数の基礎

公害防止管理者国家試験の「騒音・振動関係」を受験するにあたって、多くの人がつまずくのが常用対数(log10)を使った計算 です。
「対数なんて学生時代に勉強したけど、正直よく分からなかった」
「数字を見るとつい身構えてしまう」
そんな不安を持つ方は少なくありません。
しかし、この試験では デシベル(dB)の計算や騒音レベルの合成などで必ず常用対数を扱います。避けて通ることはできません。逆に言えば、ここをしっかり理解しておけば、得点源にすることも十分可能です。
本記事では、数学が苦手な社会人の方でも「なるほど、こういうことか」と思えるように、常用対数の基礎をできるだけわかりやすく整理します。そして、実際に試験でよく出る計算にどう活かすかまで見ていきましょう。
実際の試験や解説では、常用対数の底((log10←小さい10の部分)は省略しています。
常用対数の基礎の基礎
対数ってなに?
対数とは、「10を何回かけたらその数になるか」を表すもの です。
たとえば、
10 × 10 = 100 なので
log10(100) = 2 (10を2回かけて100になるから)
10 × 10 × 10 = 1000 なので
log10(1000) = 3 (10を3回かけて1000になるから)
こう見ると、「対数」という言葉に難しさはなく、“指数(べき乗)の逆” だとわかります。
常用対数とは?
対数にはいろいろ種類がありますが、この試験で使うのは 常用対数(log10) です。
「底(てい)が10の対数」だから 常用 と呼ばれます。
つまり、
log10(10) = 1
log10(100) = 2
log10(10000) = 4
のように、10の累乗の数はすぐに答えられる というわけです。
10の累乗でない数はどうなる?
では、10や100のようにきれいに割り切れない数はどうでしょうか。
例:
log10(2) ≈ 0.3
log10(3) ≈ 0.48
log10(5) ≈ 0.7
このように「小数」で表されます。
正確な値は電卓を使いますが、試験勉強では よく使う近似値を覚えておくと便利 です。
騒音計算とのつながり
「10を何乗したらその数になるか」という発想は、デシベル計算に直結します。
たとえば、音圧レベル L = 20 log p/p0 という式は、まさに 常用対数を使ってスケールを圧縮しているのです。
よく使う性質(公式)
常用対数は「10を何乗したらその数になるか」を表すものですが、そのままでは計算に使いにくい場面もあります。そこで活躍するのが 対数の性質(公式) です。
これを知っておくだけで、複雑に見える計算がシンプルになります。
性質①:掛け算は足し算に変わる
log(ab) = log a + log b
例:log(100 × 1000) = log(100) + log(1000)
= 2 + 3 = 5
(10の5乗=100,000 になることを意味します)
性質②:割り算は引き算に変わる
log(a/b) = log a – log b
例:log(1000 ÷ 100) = log(1000) – log(100)
= 3 – 2 = 1
(10の1乗=10 になります)
性質③:累乗は前に出せる
log(an) = n × log a
例:log(23) = 3 × log(2)
= 3 × 0.3 ≈ 0.9
(実際に log(8) ≈ 0.903 なのでほぼ一致!)
この3つで十分!
対数には他にも性質がありますが、公害防止管理者試験で必要なのはこの3つでほぼカバー可能 です。
- 掛け算 → 足し算
- 割り算 → 引き算
- 累乗 → 前に出せる
このルールを覚えておけば、複雑に見える式もスッキリ整理できます。
公害防止管理者試験での活用例
ここまでで常用対数の基本と公式を見てきました。では実際に、試験でよく出る計算例を確認してみましょう。
◆ 例1:音圧レベルの計算
音圧レベル L は、次の式で表されます。
L = 20 log p/p0
- p:測定した音圧
- p0:基準音圧 2×10-5Pa
例:
ある音の音圧が 2×10-4Paのとき、音圧レベルLは?
L = 20 log p/p0
=20 log (2×10-4 / 2×10-5)
=20 log 10
=20×1
=20dB
比を計算して、その対数をとる、これがデシベル計算の基本です。
例2:騒音レベルの合成
試験で頻出なのが「複数の音源がある場合の合成レベル」です。
例:70 dB の音源と 73 dB の音源を同時に鳴らすと、合成レベルはいくつ?
手順:
大きい方のレベル(73 dB)を基準にする。
差(73 – 70 = 3 dB)を確認。
差が 3 dB の場合、加算値は約 2 dB(試験でよく使う経験則)。
したがって、
合成レベル ≈ 73 + 2 = 75 dB
実際には log の公式を使った正確な計算で導けますが、試験対策では 差と加算値を覚えておく のが効率的です。

例3:音源が2倍になったら?
音源が同じレベルで2台になった場合、合成レベルは +3 dB となります。
これは、log(2)≈0.3を利用しているためです。
例:70 dB の機械を2台同時に稼働 → 合成は 73 dB。
ポイント整理
音圧レベルは「比を対数に変換」する式で計算
複数音源の合成は「差と加算値」を押さえるのがコツ
特に「同じ音源2つで +3 dB」というのは必ず覚えておきたい
計算をスムーズにする工夫
常用対数の計算は、慣れるまではどうしても時間がかかります。
しかし、いくつかのポイントを押さえておけば、試験本番でもスムーズに進められます。
よく使う近似値を覚える
試験問題では、log の値を暗記しておくと便利な場面があります。
特に以下は頻出です:
- log1 = 0
- log2 ≒ 0.3
- log3 ≒ 0.5 (もう少し精度がいるなら0.48)
- log4 ≒ 0.6
- log5 ≒ 0.7
- log6 ≒ 0.8 (もう少し精度がいるなら0.78)
- log7 ≒ 0.85
- log8 ≒ 0.9
- log9 ≒ 0.95
- log10= 1
デシベルの和の補正値を暗記する
| レベル差(dB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~ |
| 補正値(dB) | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
73 dB + 70 dB = 75 dB という例も、このルールで一瞬で答えられます。
常用対数表の見方
試験では「log の値を電卓で出す」よりも、常用対数表(対数表)を使う形で出題されることがあります。
ここでは、その基本的な読み方を整理しておきましょう。
常用対数表とは?
常用対数表は、1以上10未満の数の log 値を小数第4位くらいまでまとめた一覧表 です。
例:
log102 = 0.3010
log103 = 0.4771
log105 = 0.6990
このように、電卓がなくても表を見ればすぐに値がわかります。
使い方の基本
数を 1以上10未満の形に直す
例:200 の log を求めたいとき
→ 200 = 2 × 102 に変形する。
整数部分と小数部分を分ける
log200 = log(2 × 10²)
= log2 + log10²
= log2 + 2
表から log2 を探す
log2 = 0.3010(常用対数表より)
答えをまとめる
→ log200 = 0.3010 + 2 = 2.3010
よくあるつまずきポイント
整数部分(階数)と小数部分(仮数)を分けて考える
→ 「log の整数部分は 10 のべき乗を表している」と意識するとわかりやすい。
1以上10未満に直す操作 を忘れがち
→ まず「10進法でどのくらいの桁か」を確認しましょう。
対数表まとめ
常用対数表は「1~10の間の数の log 値」を調べる道具
使うときは「数を 1以上10未満に直す」 → 「整数部分はべき乗、小数部分は表から」
これができれば、電卓がなくても正確な計算が可能
まとめ
ここまで、常用対数の基礎から、試験での具体的な活用方法、そして計算をスムーズにする工夫までを整理してきました。
ポイントを振り返ると:
- 常用対数は 「10を何乗したらその数になるか」 を表すだけのシンプルな考え方
- 掛け算 → 足し算、割り算 → 引き算、累乗 → 前に出せる、という 3つの性質 が便利
- 騒音計算では 音圧レベルの式 や 騒音レベルの合成 に必ず登場する
- よく使う近似値や「差と加算値の表」を覚えておくと、試験本番でスムーズに解ける
苦手意識をなくすことが合格への近道
多くの受験生が「対数は難しい」と感じます。しかし実際には、出題される内容はパターンが決まっており、繰り返し練習すれば確実に得点できる分野です。
試験に合格した人の多くも、最初は対数に苦手意識を持っていました。大切なのは「少しずつ慣れること」です。
対数計算は、慣れればパターン化できる作業 です。
最初は戸惑っても、繰り返し練習することで「暗算のように」使えるようになります。
最後に
常用対数は、最初は取っつきにくいかもしれません。ですが一度理解してしまえば、「なぜこの式がこうなるのか」が腑に落ち、計算が楽しくなってきます。
本記事をきっかけに「対数=苦手」という意識を変えて、合格に一歩近づいていただけたら嬉しいです。
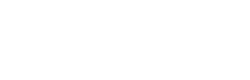


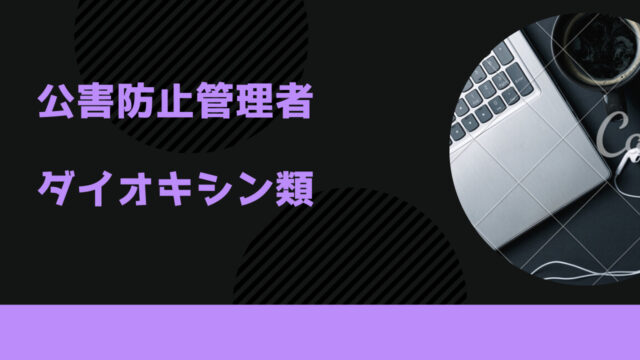
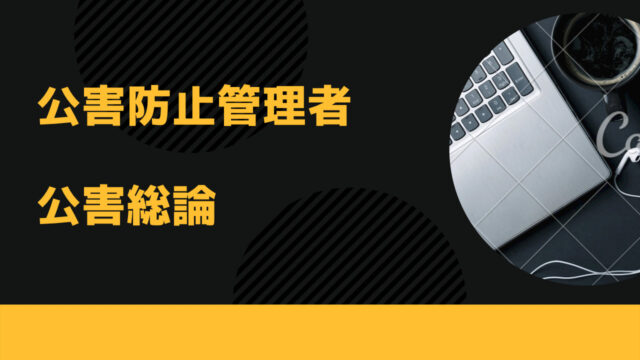
-640x360.jpg)


