公害防止管理者 ピエうさの自己採点結果
ピエうさの勉強法は、過去問をひたすら繰り返すに尽きます。
その勉強法で実際の試験は何点取れたのかを紹介します。
- 平成30年度(第48回) 大気関係第1種公害防止管理者試験 合格
- 令和元年度(第49回) 騒音・振動関係公害防止管理者試験 合格
- 令和2年度(第50回) 水質関係第1種公害防止管理者試験 合格
- 令和3年度(第51回) ダイオキシン類関係公害防止管理者試験 合格
平成30年度(第48回) 大気関係第1種公害防止管理者試験
| 試験科目 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |
| 公害総論 | 15 | 14 | 93.3% |
| 大気概論 | 10 | 10 | 100% |
| 大気特論 | 15 | 12 | 80% |
| ばいじん・粉じん特論 | 15 | 13 | 86.7% |
| 大気有害物質特論 | 10 | 6 | 60% |
| 大規模大気特論 | 10 | 10 | 100% |
初めての公害防止管理者試験の結果です。
公害総論の免除が無く、大気1種は科目数が公害防止管理者の区分の内で一番多いですが、何とか合格できました。
大気有害物質特論はギリギリで、試験中は「落ちたかも…」と焦っていました。
令和元年度(第49回) 騒音・振動関係公害防止管理者試験
| 試験科目 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |
| 公害総論 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 騒音・振動概論 | 25 | 23 | 92% |
| 騒音・振動特論 | 30 | 22 | 73.3% |
このブログで解説している騒音・振動関係です。
騒音・振動関係は計算問題の比率が高く、他の試験とは性格が違っています。
そのせいか、騒音・振動特論は、試験の最後の時間まで計算していました。
令和2年度(第50回) 水質関係第1種公害防止管理者試験
| 試験科目 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |
| 公害総論 | 15 | 免除 | 免除 |
| 水質概論 | 10 | 10 | 100% |
| 汚水処理特論 | 25 | 22 | 88% |
| 水質有害物質特論 | 15 | 11 | 73.3% |
| 大規模水質特論 | 10 | 7 | 70% |
大気と騒音・振動は、機械や工学のような内容が割と出題されますが、水質は化学の出題が多くあります。
ピエうさは、化学系の学部出身なので、勉強の抵抗は一番なかったと思います。
大気1種と水質1種を取得できましたので、公害防止主任管理
令和3年度(第51回)ダイオキシン類関係公害防止管理者試験
| 試験科目 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |
| 公害総論 | 15 | 免除 | 免除 |
| ダイオキシン類概論 | 15 | 12 | 80% |
| ダイオキシン類特論 | 25 | 24 | 96% |
このブログで解説しているダイオキシン類関係です。
大気と水質は受かっていたので、勉強量は一番少なく済みました。
どの分野も概論は簡単で、特論は難しい傾向にありますが、令和3年のダイオキシン類は概論の方が難しく感じました。
まとめ
この記事を書くにあたり、ピエうさが実際の試験会場で解いてきた問題用紙を見返しました。
過去問を何度も繰り返すことは一番大切ですが、受験をしている時も合格率を高めようとして色々行っていることがわかりました。
問題文をきちんと読む
公害防止管理者の問題文で一番多い問われ方は、「~のうち、誤っているものはどれか。」です。
過去問演習していても、回数を重ねると誤っている選択肢の記述を覚えてしまうほどです。
しかし、時々「正しいものはどれか。」となっている問題もあります。
問題文をよく読まずに選択肢を見てしまうと、記載が誤っている一つ目の選択肢を見た瞬間にこれが正解だと勘違いすることになります。
ピエうさも過去問演習ではよくやらかしていたミスなので、本番では落ち着いて問題文を読みましょう。
選択肢は全て確認する
選択肢を全部確認しても、正解が絞り込めないないことがよくあります。
しかし、それぞれの選択肢に書かれていることの全部に見当がつかないことは稀ではないでしょうか。
あてずっぽうで一つを選ぶと、公害防止管理者試験の選択肢は5択なので、正解確率は20%です。
部分的でも知っていることを探して、少しでも選択肢を落とすことができれば、正解確率は25%から33%や50%にまであげることも可能です。
公害防止管理者試験の範囲は広いので、全てを網羅することは不可能だと思います。
わからないなりに少しでも正解確率を高めて、合格に近づけるようにしましょう。
計算問題は必ず手を動かす
計算問題は、捨て問にしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
大気や水質は計算問題が少ないので、知識問題を頑張れば、計算問題を全て捨てても、合格基準の6割は確保できます。
しかしそれでは、膨大な知識が必要になってしまいます。
一方で、大気や水質の計算問題は、少しの努力で点数化しやすいことが多くあります。
公式に代入するだけで答えを求められる
公式を覚えるだけで答えがわかるので、これを捨てるのはもったいないですね。
単位から簡単な割り算や掛け算で計算方法を推測できる
問題文の数字には単位(kg/㎥・日など)が記載されています。
容積が〇㎥で一日当たり〇kg発生しているなどの情報があれば、割り算でその単位になることがわかります。
実際に解くときは、数字だけでなく単位も併せて書き、単位も割り算や掛け算で消去しながら計算していけば、設問の単位と一致することで正しく計算されていることが確認できます。
出題パターンが毎年一緒
大気特論の3、4問目は、ほぼ毎年燃焼の計算問題です。
化学式と空気量からガス量などを求める問題が多く、出題パターンが限られています。
パターンを一つ覚えれば、あとは数字がかわるだけです。
パターンを覚えるまでは大変ですが、一度覚えてしまえば確実に点数がとれます。
とりあえず手を動かす
騒音・振動関係は計算問題メインのため、覚えないといけない公式が多くあります。
そうなると、いくつかうろ覚えになってしまう公式もあると思います。
また、公式をそのまま使えないような問題が出題されることもあります。
それでもテキトウに数字を組み合わせていくと、本人もよくわからないのに、選択肢にある数字に辿り着くことがあります。
ピエうさの経験則では、そういう数字は割と当たっています(笑)
これから受験される方も試験の最後の時間まで諦めずに頑張ってください!
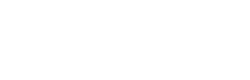

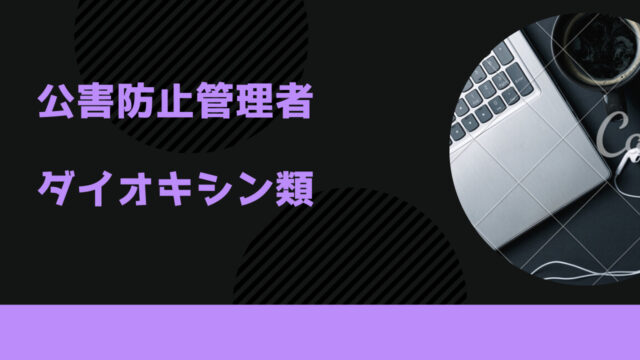




-640x360.jpg)
お疲れ様です。
令和5年の試験が終わったばかりですが
今年のダイオキシンの問題、解説はアップ予定ありますか?
時期は明言できませんが、令和5年度の解説も作成する予定です。
(2023年)R5.騒音振動概論問25 地盤を伝播する波動について 過去問の解説を見てもよくわからないので教えてください。
それぞれ表現の仕方ですが異なっています。
(1)P波は波の進行方向に平行な運動である。
※過去問では波の進行方向に前後運動すると。
(2)S波は波の進行方向に垂直な運動をする。
※過去問では直角方向(鉛直方向)と。
(5)ラブ波は波の進行方向に対して平行な水平運動を
する。
※過去問では波の進行方向に対して、直角な水平運動と。
また、垂直に振動する。
とも書いてありました。
いずれにせよ、この問題では(5)が誤りでした。
P波とS波については、表現は異なりますが、本質的には同じことを言っています。
それぞれ画像検索していただくと、分かりやすい図がありますので、言葉よりもイメージで覚えてください。
公害防止管理者等国家試験 騒音・振動関係 重要ポイント & 精選問題集ではP波、S波、レイリー波は詳しく載っていますが、ラブはあまり記載されていません。
個人的には、(1)〜(4)は確実に押さえ、消去法で(5)が選べれば十分かなと思います。
R5 騒音振動特論問29 の解説を読んだのですがわからない部分があるので教えて下さい。
https://pierre-usagi.com/kougai-r5-souon-shindou-tokuron-29/
(解説)
20nlogr/r0の部分は、距離減衰を示します。
8.7λ(r-r0)の部分は、内部減衰を示します。
内部減衰係数は距離減衰の部分に入っていないので、距離減衰の測定には不要と考えられます。
(質問)
20nlogr/r0は広がりによる幾何減衰と言われていますが
幾何減衰は距離減衰と同じことになりますか?
距離減衰=幾何減衰+内部減衰
と公式になっているので上記の解説がよくわかりませんので教えて下さい。
ご指摘のとおり、距離減衰=幾何減衰+内部減衰なので、解説が誤っていました。
私の調べた範囲ですが、解説を修正しましたので、ご確認よろしくお願いします。
わかりました。
r5 騒音振動特論 問19で解説を読んだのですがでわからないところがあるので教えてください。
(解説)質量が2倍になるので、mは2mとなります。
f=1/2π√(k/m)→f=1/2π√(k/2m)
このとき、fが1/2となるのは、kが1/2のときとなります。
なぜ、このときfが1/2となるのは、kが1/2の時であるのか?
わかりませんので補足説明お願いします。
r5 騒音振動特論 問19に式変形を含めて詳しく記載しました。
ありがとうございます。
しかし、ここに間違えがあると思いますので教えてください。
このときfが1/2となるので、ばね定数がn倍となったと考えます。
f=1/2π√(k/m)
→f/2=1/2π√(nk/2m)=1/2π√(nk/m)×√(n/2)=f×√(n/2)
1/2=√(n/2)
nが2つ出てくるのは間違いでは?1/2π√(nk/m)×√(n/2)
また、上の式ではfが1/2倍されたときkは√n/2と言うことを表していますか?
すいません。自分は数学が苦手なので。
ありがとうございます。
しかし、ここに間違えがあると思いますので教えてください。
このときfが1/2となるので、ばね定数がn倍となったと考えます。
f=1/2π√(k/m)
→f/2=1/2π√(nk/2m)=1/2π√(nk/m)×√(n/2)=f×√(n/2)
1/2=√(n/2)
nが2つ出てくるのは間違いでは?1/2π√(nk/m)×√(n/2)
また、上の式ではfが1/2倍されたときkは√n/2と言うことを表していますか?
ご指摘ありがとうございます。
単にnの消し忘れなので、投稿を修正しました。
問題文の条件は、質量が2m、振動数がf/2となったとき、kは何倍になるかを問われています。
今回の解き方では、そのときn倍になったとしています。
したがって、fが1/2倍されたとき、kはn倍となります。
わかりました。
ありがとうございます。
この問題では、高さ0.5mから落下した際の最大加速度を問われています。
r5 騒音振動特論 問18で解説を読んだのですがでわからないところがあるので教えてください。
>>最大加速度なので、上記加速度aはv0ωの場合に該当します。
また、v0はエネルギー保存則のv=√(2gh)になります。
なぜ、最大加速度でa=V0ωの式が出てくるのでしょうか?
加速度はsinの関数で表されるため、最大値はsinが±1のときになります。
加速度a=-y0ω2sin(ωt)=-v0ωsin(ωt)のため、最大値はv0ωとなります。
この問題は、個人的に捨て問にしても良い難易度と考えています。
余裕があって物理が得意な方以外は、深追いしない方が得策と思います。
わかりました。
私は物理が苦手なので深追いしません。
r5 騒音振動特論 問18で解説を読んだのですがでわからないところがあるので教えてください。
この問題は公式 f=C/4Lを覚えていて解くよりも解説にあったsinの考え方で解いた方が宜しいでしょうか?
以下の所がよくわかっていない物で。
>>sinの関数であることから、Rが最大となるとなるのは、klが90度(π/2)、270度(3π/2)、450度(5π/2)…のときとなります。
https://pierre-usagi.com/kougai-r5-souon-shindou-tokuron-2/
上記、ページの解説を細かく書いたので、参考にしてください。
また、質問がある場合は、該当する問題の記事に書き込んでいただけると、
他の方も参考になると思いますので、よろしくお願いします。
あと、公害防止管理者試験 騒音振動は物理が苦手な人でも合格は得られるのでしょうか? 自分は物理が苦手ですが、デシベルの合成の問題は解けます。
最低限、指数・対数の計算だけ出来る(問題の解説を理解出来る)ようであれば、物理が苦手でも合格可能です。
過去問5年分くらいの出題パターンを覚えれば、かなり合格に近いと思います。
反対に、高校物理ではデシベル計算をほぼ習わないと思うので、
物理が得意なだけでは合格出来ないでしょう。
わかりました。
R5 騒音・振動特論 問13についてですが、なぜ、時間帯補正等価騒音レベルについては電話帳や重要ポイント&精選問題集に載っていないことなのか?
載っていないのでムズカシク感じます。
https://pierre-usagi.com/kougai-r5-souon-shindou-tokuron-13/
解説ページに詳細を追記したのでご覧ください。
初めまして、ピエうさ様。
遅くなりましたが、こちらの過去問サイトを活用させていただき、昨年の騒音振動に合格することが出来ました。(総論概論特論ともにボーダーギリギリでしたが)
私自身、参考書よりも過去問で勉強するタイプなので大変重宝致しました、
こちらにある過去問を片っ端から2,3周解かせてもらい、難しい計算等すべてを理解することは不可能でしたが、頻繁に出る所を何とか抑えることが出来ました。
いろいろと丁寧なご解説、ありがとうございました!
合格おめでとうございます。
私が市販の参考書をもとに身につけた程度の知識での解説でしたが、参考にしていただいて光栄です。
今後、周りの方で公害防止管理者の受験を考えている方がいるようであれば、このサイトを紹介していただけると嬉しいです。
コメントありがとうございました。